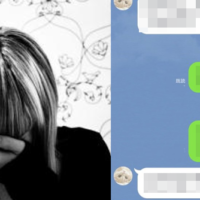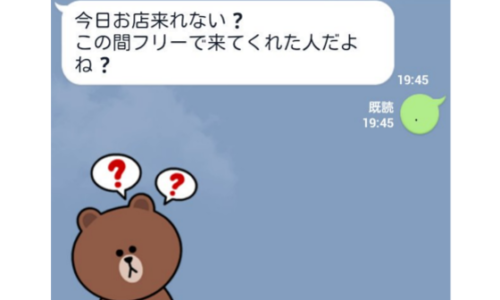民事裁判の建前は弁論主義と言って、裁判官はあくまでも当事者とその弁護士の
主張や提出する証拠がなければ、勝手に真実を暴いて判決を下すことは許されない。、
あくまでも法の上での真実、つまり相対的な真実が必要である。
今回の事例だと、離婚裁判というのは私的な損得の問題を解決するためのもので、
離婚訴訟の解決に役立つ、そして当事者が納得できる範囲の真実さえあればいいわけで、
その真実は絶対的な真実である必要はまったくないというのが法の立前なのだと。
だから、妻は離婚したくないって言ってるけど、本当はこうだったのではないの、とか裁判官が勝手に
判決を下してしまう事は許されない。
あなたは日本は三審制なんだから上告できるはず、したいと言う。
けれど、三審制といっても、事実の取り調べは第一審ですべて行われるので
いったんここで事実として認定されてしまうと、この事実が裁判所の事実となってしまい、
「もう一度、最初から話し合いがしたい」との願いを受け入れてくれる意味での
三審ではない。
一審の時、提出したカウンセリング継続の書類や、夫が戻ってくれるならやり直すための
プログラム等、必要だと思われる書類は全部提出し、本人尋問もお互い行った。
その一審で出た判決がもっとも重要であり、ほとんどの裁判は、この一審で確定となる。
ここで、相対的であれ、裁判所の真実、つまり判決が決まるという事なのだ、と。